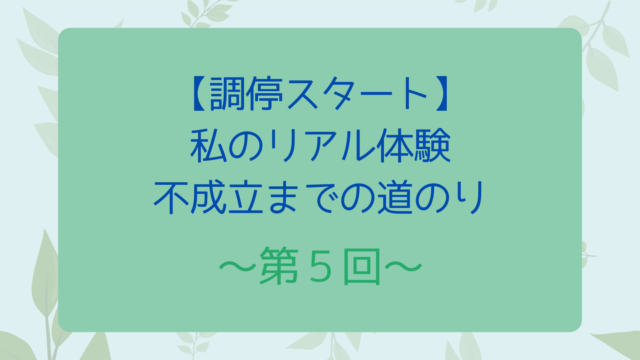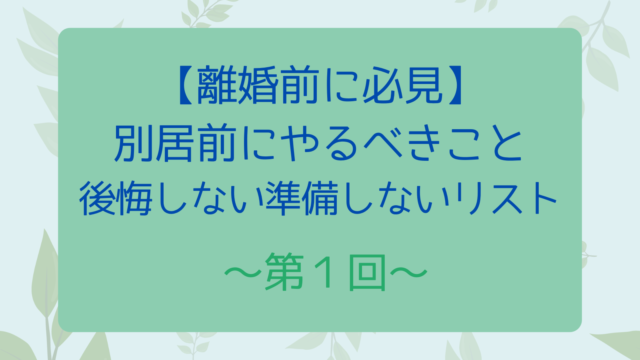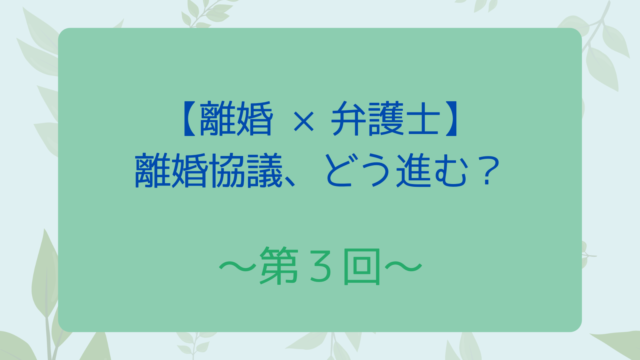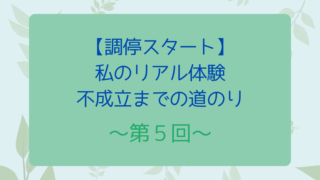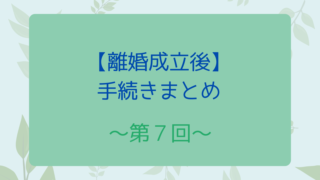離婚裁判の流れと費用【ついに審判確定】
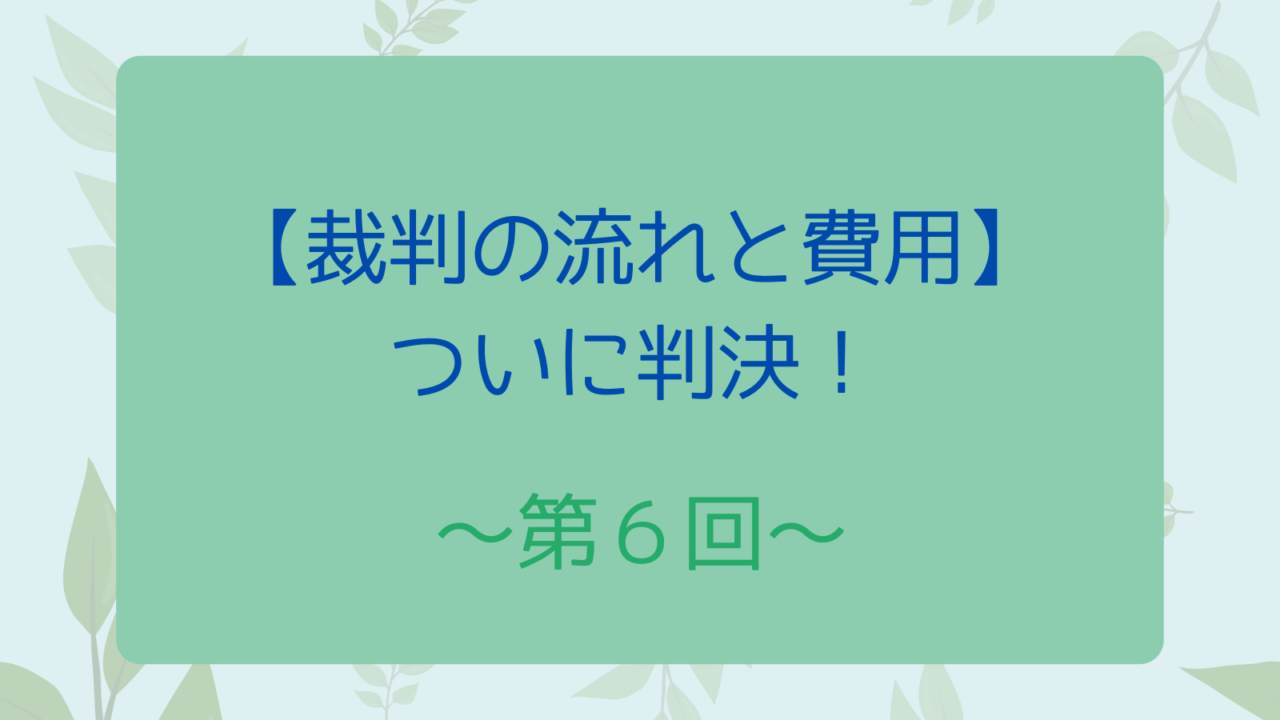
この記事は「離婚準備シリーズ」の第6回です。
今回は、調停不成立のあとに始まった「離婚裁判」について、私自身の経験をもとに流れや気持ちの整理方法をまとめました。
離婚裁判を検討している方や、先の見えない状況に不安を感じている方の参考になれば嬉しいです。
調停不成立のあと、裁判を選んだ理由
私は当初から「離婚裁判」を望んでいました。話し合いでは進展が見込めず、費用がかかっても離婚・改姓し、新たな生活を始めたかったからです。
ただし、離婚裁判を行うには手順が必要で、協議→調停→裁判の順で進めなければなりません。
また、離婚理由が「飲酒」「疾病」の場合、別居後2〜3年経たなければ裁判で認められにくいと弁護士から説明を受けていました。
結果、予想通り調停不成立となり、ようやく裁判へ進めることになりました。
裁判に向けた法テラス手続きと費用
裁判に進むためには再び弁護士費用が発生します。そのため、法テラスへの援助申請を再度行う必要があります。
さらに、弁護士に裁判手続きの委任をする委任状の提出も必要となりました。
- 📝 令和6年7月:弁護士から書類一式が送られてきたため提出
- 📩 令和6年9月:法テラスより決定書(援助内容と金額)到着
- 💰 200,000円を9月中旬に一括振込(通常は月額10,000円の分割可)
裁判に向けた準備と打ち合わせ
10月2日、弁護士から「裁判準備を進めたい」との連絡があり、収入印紙代13,000円の納付についても説明を受けました。
一括納付または支払い猶予の申請のどちらかを選べるとのことで、私は打ち合わせ時に現金で納付しました。
打ち合わせは10月9日15:30〜、約30分程度で行われ、主に離婚に至るまでの詳細な経緯を確認されました。
あらかじめ内容を紙にまとめて持参していたため、説明もスムーズに行えました。
訴状提出と第1回裁判期日
約3週間後、弁護士から訴状案がメールで届き、内容確認後に提出。
その後、11月5日に「第1回期日は11月29日11:45から」と連絡がありました。
この回は弁護士のみが出廷し、私は裁判所へ行く必要はありませんでした。
裁判中に必要となった追加の手続き
保育園の現況届に添付するための医師の診断書が再び必要となり、弁護士を通して相手に通知文を送付。
12月中旬に無事診断書が届きました。
第1回裁判期日と相手の主張
11月29日夜、弁護士から電話連絡があり、相手は以下の2点を主張してきました。
- 面会交流の要求
- 財産分与の請求
面会交流については「相手が調停を申し立てれば応じる」と回答。
財産分与については、弁護士から「別居時点の財産を折半が基本」との説明があり、現時点では対応不要とのことでした。
ついに…審判確定の連絡
12月19日夜、弁護士から「審判が確定した」と連絡がありました。
ついに離婚が認められたのです。
裁判所からの書類が届き次第、市役所で離婚手続きをするよう案内されました。
まだ正式な書面は届いていませんが、「これでやっと…」と安堵した気持ちが込み上げました。
まとめ|別居から約2年9か月、ようやく離婚成立へ
長かった裁判までの道のり。別居から約2年9か月、ようやく審判が確定しました。
正式な離婚手続きはまだですが、ここまで来られたことに大きな意味があります。
🔜 次回予告
次回は「市役所での離婚手続きと、関係各所への届け出」についてまとめていく予定です。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。
同じように悩んでいる方の一歩につながれば嬉しいです。